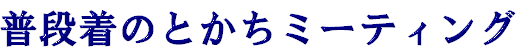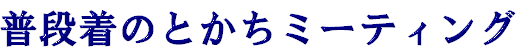「回想の依田勉三」(三原武彦)を読んで
嶺野侑(十勝史談会顧問)
オベリベリで断絶
半世紀を経て対座した勉三とリク
感動の歴史ドラマ
十勝日日新聞に掲載された三原武彦の『回想の依田勉三』は、今にして思えば“ああ、そうだったのか”と納得できる資料で大きな発見であると思う。
ちなみにこの新聞は、昭和25年ころ創刊、社長笹谷常咲(戦前の道会議員)、専務取締役内木宮多良(時事放声社社長、後帯広ガス社長)、常務取締役・編集局長丸谷金保(後池田町長)という布陣だった。
しかし、戦後の経済的混乱のせいか、発刊後たちまち経営難に陥り、一年足らずで廃刊に追い込まれた。それでも営業部長平野竜が一人で発刊を続けていたようだが、題字の下の発行人は、平野竜となっているので、そのころの新聞であろう。
さて大きな発見とはなにか。
依田勉三は大正14年12月12日、帯広町西2条10丁目の自宅で74歳の波乱の生涯を閉じた。最後を看取ったのは勉三の最初の妻リク、養嗣子八百などだったが、『晩成社には一銭の金も一坪の土地もない。晩成社は解散する。しかし十勝野は・・・』と絶句、息を引き取ったというのがこれまでの通説だった。勉三の最後を飾るにふさわしい言葉は物語となり、私自身も文章や講演で引用してきた。
三原の文章によると、この言葉は関東大震災で東京帝国大学を退学、廃墟の東京を後に、はるばる勉三を頼り帯広にたどり着いた三原青年に、勉三が発したものであることが分かる。とはいっても勉三の思いに共感する気持ちには、いささかも変わりない。
もう一つ。途別水田に成功後、内助の功が高かった二度目の妻サヨは、突然、脳いっ血で倒れて他界。続いて勉三自身も脳いっ血で不自由なからだになってしまった。このため最初の妻リクを介護に呼び寄せたのは、養嗣子八百であるといわれてきた。
三原は勉三が風の便りで再婚したばかりの夫が亡くなり、生計が苦しくなったことを知り、勉三自身の意思で、三原が使者となり迎えて来た事実を記している。かつて若い日の夢を晩成社に求めた二人が、義絶し半世紀を経て対座、『苦労したろう』と勉三、『あなたも』と、リク。二人の老いの目には、光るものがあったという。これこそ歴史のドラマというべきものであろう。
|